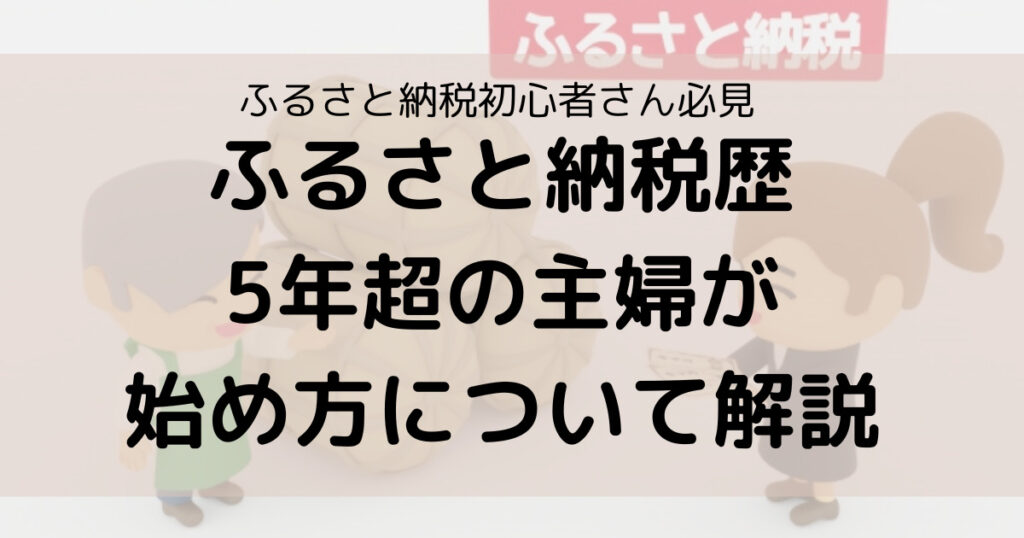「ふるさと納税をやってみたいけど何から初めていいのか分からない…」
「ふるさと納税の仕組みを知りたい」
「ふるさと納税の始め方を分かりやすく教えて欲しい」
税金がお得になると話題になっているため、ふるさと納税をする人は年々増えてきています。まだ制度を利用していない人でも、ふるさと納税というワードを1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
ふるさと納税をやってみたいけど、実際のやり方や仕組みについて知らないという方は少なくないはず。
初心者にありがちなのが、「ふるさと納税は節税になる」という誤解。実は、住民税はお得になるものの、ふるさと納税で節税できるわけではありません。この記事では、ふるさと納税歴5年以上の私が実際のやり方について分かりやすくご紹介しています。節税できないならなんでみんな使っているの?という疑問も、この記事を読めば解決できますので、ぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税とは
Contents
ふるさと納税とは、応援したい地域(自治体)に寄付ができ、返礼品がもらえる仕組みのことです。寄付したお金の使い道を私たち納税者が選択することができるのも特徴です。送られてくる返礼品は、その地域の特産品などで、肉や魚といった食品から日用品まで多くあります。寄付額の3割程度相当が、返礼品としてもらえます。
このふるさと納税は、私たちが普段納めている住民税の一部からおこなうことがでるのが特徴です。住民税はただ払って終わりですが、ふるさと納税の場合、返礼品がもらえるためお得感があり、昨今話題となっています。
具体的な仕組みや目的については以下でご紹介します。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、私たちが住民税として支払っている金額の一部で、応援したい地域に寄付が可能です。よく「ふるさと納税は節税になる」と勘違いされている方もいますが、ふるさと納税は厳密にいうと節税ではありません。
住民税はだいたい課税所得(手取り年収)の10%が請求されるような仕組みとなっています。年収400万円の場合の課税所得(手取り年収)は、315.6万円です。年収400万円の方は、控除などが全くない場合、ざっくり計算すると毎月2.6万円の住民税を払うことになります。
毎月支払う住民税の一部をふるさと納税の寄付にあてることで、寄付先からの返礼品がもらえるようになります。ただ単に住民税を支払うより、返礼品の分がお得になるのがふるさと納税の仕組みです。
ふるさと納税の目的
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/policy/
総務省|ふるさと納税ポータルサイトでは、ふるさと納税には以下の3つの意義があると言及しています。
納税者が寄付先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度である。そのことより、税に関する意識が高まり納税の大切さを考える貴重なきっかけとなる。
生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域やこれから応援したい地域へも力になれる制度である。人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援となる。
自治体が国民に取り組みをアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。このことにより、選んでもらうに相応しい、地域のあり方を改めて考えるきっかけと繋がる。
このことより、ふるさと納税は「私たち納税者の税金に関する意識の向上」「ふるさとへの恩返し」「地域の活性化」を目的としているといえるでしょう。
返礼品目的でふるさと納税を始めるのもよいですが、ふるさと納税が税金を考えるきっかけになるのもよいですね。
ふるさと納税の魅力とは
ふるさと納税歴5年超の私が感じているふるさと納税の魅力は以下の3つです。
返礼品がもらえる
住民税や所得税が安くなる
生まれ故郷や頑張って欲しい地域を応援できる
それぞれ詳しくご紹介していきますね。
返礼品がもらえる
これまでなんとなく支払っていた住民税ですが、一部をふるさと納税にあてることで返礼品がもらえるようになります。
ふるさと納税の返礼品は、食品や日用品、家具など多岐に渡ります。応援したい自治体を選んでふるさと納税するのはもちろん、返礼品からふるさと納税をしたい自治体を選ぶのもOKです。
ふるさと納税で食費や日用品代を浮かすことが可能です。
住民税や所得税が安くなる
住民税の一部をふるさと納税にあてることで、その分払う税金が安くなります。なぜ安くなるのかというと、普段支払っている住民税をふるさと納税で前払いしているからです。住民税の一部をふるさと納税にあてることで、返礼品をもらえる上に翌年の住民税が安くなります。
住民税の一部をふるさと納税にあてれるイメージです。
生まれ故郷や頑張って欲しい地域を応援できる
ふるさと納税は、生まれ故郷や応援したい地域など自分の好きな自治体へ寄付できるのが魅力の1つです。例えば、災害に見舞われた地域へ何かしたいけど、現地には出向くことができないし…といった場合、ふるさと納税を活用することでその地域を応援できます。
納税の際に寄付の使い道も選択でき、税金について改めて考えるきっかけにもなるでしょう。
災害復興などの応援もよいですよね。
ふるさと納税のデメリットと注意点
魅力がいっぱいのふるさと納税ですが、デメリットや注意点もあります。ふるさと納税歴5年の私が感じているふるさと納税のデメリットと注意点は以下の3つです。
手続きが面倒
寄付は一旦手出しが必要である
上限額を超えての寄付は住民税の控除対象外となる
それぞれ詳しく解説します。
手続きが面倒
ふるさと納税は寄付をしたら終わりではありません。ワンストップ特例申請書または確定申告を活用して、「私はこの地域に〇〇円ふるさと納税したよ〜」と申告する必要があります。手続きを怠るとただの寄付となってしまい、住民税の控除を受けることができません。
不慣れなうちは、この一連の手続きが面倒と感じる方もいるかもしれませんが、慣れてしまえばワンストップ特例申請も確定申告もあっという間にできます。
最初は大変かもしれませんが、頑張って慣れていきましょう。
寄付は一旦手出しが必要である
ふるさと納税は、住民税の前払いです。通常であれば、前年度の1〜12月の収入に応じて、その次の年の5月以降から徴収が開始されます。
この5月以降に徴収が開始される住民税の一部を、前年の1年間の間にふるさと納税することで控除が受けられる仕組みとなっています。そのため、前払い分の手出しが必要になるのです。
上限額を超えての寄付は住民税の控除対象外となる
ふるさと納税の上限額を超えて寄付した場合、上限額を超えた部分は控除の対象外となるため注意が必要です。心配な方は、上限額より少し安めに寄付をするかその年の収入が確定する年末にふるさと納税をすることをおすすめします。
上限額のシュミレーションをしてからふるさと納税してくださいね。
ふるさと納税の始め方を7つのステップで解説
ここでは、初めての方でもスムーズにふるさと納税を始められるように分かりやすく7ステップで解説しています。
寄付金上限額を調べる
ふるさと納税をするサイトを選ぶ
寄付する団体を選ぶ
自治体に寄付する
返礼品を受け取る
寄付金証明書(とワンストップ特例制度の書類)を受け取る
控除の手続きをする
それぞれ詳しく解説していきます。
STEP1.寄付金上限額を調べる
まずは自分の寄付金上限額を知っておく必要があります。寄付金上限額は年収によって変わります。
自分の年収が分からないといった方は、前年度の源泉徴収票を見てたり、会社の経理担当の方に聞いたりして調べてみてください。年末まで待って自分の給料を計算するのでもよいでしょう。
ここでの年収とは、手取りではなく総支給額になります。自分の年収が分かったら、実際に寄付金上限額を調べましょう。寄付金上限額を調べるのにおすすめなのが、ふるさとチョイスの控除上限額シュミレーションサイトです。
かんたんシュミレーションでは、自分の年収と家族構成を入力するだけでおおよその上限額を計算できます。より正確な上限額を知りたい場合には、控除上限額シュミレーションに必要事項を入力して計算してみてください。正確な上限額を計算する場合には、社会保険等の金額や生命保険控除料の金額などを入力する欄があります。もし、この金額が分かる場合には入力して計算することで正確な金額を算出することができます。
STEP2.ふるさと納税をするサイトを選ぶ
ふるさと納税をするサイトは、いくつかあります。中でもおすすめなのは以下の4つです。
楽天市場やYahoo!ショッピングは、買い物感覚でふるさと納税ができる魅力があります。一方のふるさと納税サイトであるさとふるやふるさとチョイスは返礼品の掲載数が多いのが魅力です。
STEP3.寄付する自治体を選ぶ
ふるさと納税をするサイトを選んだら、寄付する自治体を選びましょう。実家のある故郷や応援したい自治体を選ぶのもよいですし、好きな返礼品で寄付する自治体を見つけるのでもよいです。
私自身は、返礼品で寄付する自治体を決めています。
ここで注意しておきたいのが、現在住民票のある自治体への寄付はふるさと納税の対象とならないことです。自分の住んでいる自治体に納税してしまうとただの寄付となり、住民税の控除対象とならないため注意しましょう。
STEP4.自治体に寄付する
寄付する自治体が決まったら、実際に寄付をしていきましょう。この時に寄付金の使い道について選択する項目があります。自分の寄付するお金がどんな用途に使われて欲しいのか選びましょう。
また、ワンストップ特例を利用する場合には自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」が必要です。ワンストップ特例とは、寄付する自治体が少ない場合に確定申告をしないで済む制度です。寄付の際に「ワンストップ特例申請書を希望しますか?」と選択する項目があります。確定申告ではなくワンストップ特例を利用しようとお考えの方は、必ず「希望する」とするようにしてください。
ここで「希望する」を選択したからといって、必ずワンストップ特例で申請しないといけないわけではありません。ワンストップ特例を利用するか確定申告するか分からないといった方は、ワンストップ特例申請書をもらっておくと安心です。
STEP5.返礼品を受け取る
無事に寄付したら、自治体より返礼品が送られてきます。返礼品の内容によっては、寄付後すぐに送られてくるものや2〜3ヶ月後に送られてくるものなどさまざまです。
返礼品の送付時期に関しては寄付する際のページに記載されていますので、寄付の際に確認するようにしましょう。
h3 STEP5.寄付金証明書(とワンストップ特例申請書)を受け取る
返礼品と寄付金証明書・ワンストップ特例申請書は別々に送られてくる場合がほとんどです。寄付金証明書とワンストップ特例申請書は郵送で送られてきます。
ワンストップ特例の申請をする場合には寄付金証明書の出番はありません。しかし、確定申告をしなければならない状況になった際に寄付金証明書が必要となるため、大切に保管しておくことをおすすめします。
STEP6.控除の手続きをする
ふるさと納税をする自治体が5つ以内であれば、ワンストップ特例制度を利用できます。ふるさと納税をする自治体が6つ以上になる場合や医療費控除申請や住宅ローン控除の初年度などで確定申告が必要になる場合には、確定申告が必要になります。ワンストップ特例制度と確定申告の違いについてそれぞれ詳しく説明します。
ワンストップ特例制度
ふるさと納税をした後に、確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる仕組みです。自治体から送付されてくるワンストップ特例申請書に必要事項を記入し、本人確認書類を同封して返送することで、手続きが完了します。1月〜12月分のふるさと納税分は翌年の1月10日必着で返送する必要があります。ここを過ぎてしまうと、申請が無効となるため注意が必要です。
こちらが実際の申請書です。赤枠の必要事項を記入し、個人番号確認書類と本人確認書類を添付して返送するだけになります。マイナンバーカードを取得済であれば、スマホでワンストップ特例申請をおこなうことも可能です。
確定申告
1月〜12月にふるさと納税をした分を確定申告する場合は、翌年の3月15日までに確定申告する必要があります。以下に該当する場合はふるさと納税の確定申告をする必要があります。
寄付先の自治体が6つを超えてしまった
ワンストップ特例申請書を提出し忘れた
ワンストップ特例申請書は提出したけど、別のことで確定申告が必要になった
これらに該当する場合は、寄付金控除を受けるために必ず確定申告をしましょう。特に3つ目に該当する場合には、確定申告が漏れやすいため注意が必要です。
ワンストップ特例申請書を提出していても、医療費控除など他の用件で確定申告が必要になった場合、ワンストップ特例は無効となってしまいます。一緒に確定申告を実施しなければ、寄付金控除を受けられません。確定申告をする際には、寄付金証明書が必要であるため、翌年5月以降に寄付金控除を受けられているか確認できるまで大切に保管しておきましょう。
ふるさと納税おすすめサイト3選
ふるさと納税をするのにおすすめのサイトを3つご紹介します。個人的には、ネットショッピング感覚でふるさと納税できる楽天市場やYahoo!ショッピングがおすすめです。
楽天市場
https://event.rakuten.co.jp/furusato/
我が家は毎年楽天市場でふるさと納税をしています。普段から楽天市場でネットショッピングをする機会が多かったため、ふるさと納税をする際にもスムーズにおこなうことができました。楽天市場のふるさと納税はお買い物マラソンやスーパーセールなどで大きなポイント還元を受けられるのが嬉しいメリット。普段からネットショッピングで楽天市場を使っているという方は、楽天市場でのふるさと納税がおすすめです。
Yahoo!ショッピング
https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/furusato/
楽天市場は使っていないけど、Yahoo!ショッピングを利用しているという方はYahoo!ショッピングでのふるさと納税がおすすめ。Yahoo!ショッピングでも、楽天市場同様、ポイント還元があるため、ふるさと納税をしてTポイントやPayPayポイントを貯められます。ソフトバンクユーザーやYモバイルユーザーは、ポイント還元が高くなるため、Yahoo!ショッピングでのふるさと納税がおすすめです。
さとふる
さとふるなどのふるさと納税サイトは返礼品の掲載数が多いのが特徴です。たくさんの返礼品からふるさと納税する自治体を探したいといった方は、ふるさと納税サイトでの寄付をおすすめします。
ふるさと納税おすすめ返礼品4選
ここでは、ふるさと納税歴5年の私がおすすめする返礼品を4つご紹介します。
お米
毎日の食卓に欠かせないお米。家族の特に世帯の人数が多いご家庭は、お米の消費量が多いのではないでしょうか。4人家族の我が家はそんなお米がふるさと納税の大定番となっています。年間消費するお米の8割はふるさと納税で賄っています。自宅に直接届くため、スーパーに買いに行く必要がありません。小さなお子さんのいるご家庭ではお米を買いに行くのも大変だと思うため、ぜひふるさと納税を活用することをおすすめします。
お肉
我が家は、高くて手の出ない牛肉はふるさと納税に頼っています。すき焼きに肉じゃが、ふるさと納税のお肉は美味しいものばかりで、食べると幸せな気持ちになります。焼き肉用のお肉や高級黒毛和牛の返礼品もありますので、ぜひお好きなお肉を探してみてください。
フルーツ
お子さんのいるご家庭に特におすすめしたいのがフルーツ。子どもはみんなフルーツが好きですよね。でもスーパーで買うと高くてたくさんは買えない…。そんなときはふるさと納税の出番です。
私は、ふるさと納税のイチゴが大好きです。子ども達もみんな大好きなので、届いたその日に全部なくなってしまうなんてことも。イチゴ以外にもたくさんのフルーツが返礼品にありますので、ぜひ好きなフルーツを探してみてくださいね。
ティッシュ
どこのお家にも必ずあるティッシュ。そんなティッシュもふるさと納税の返礼品としている自治体があります。消耗品であるためいくらあっても困ることはありませんが、割と大量に届くため、保管場所に注意が必要です。もちろん、ティッシュだけではなくトイレットペーパーの返礼品もありますよ。
ふるさと納税に関するよくある質問
ここではふるさと納税に関するよくある以下の3つの質問について回答しています。
手出しの2,000円ってどういう意味なの?
住宅ローン控除があってもふるさと納税できるの?
育児休暇中にふるさと納税してもお得になるの?
ふるさと納税したのに控除手続きを忘れたらどうなるの?
それぞれ詳しくみていきましょう。
手出しの2,000円ってどういう意味なの?
簡単にいうと、ふるさと納税をする場合は通常の住民税+2,000円が必要になりますといった意味になります。この2,000円がよく分からないといった方は多くいますが、あまり深く考える必要はありません。
この2,000円はふるさと納税をする上で必要な手数料と考えておくとよいでしょう。
住宅ローン控除があってもふるさと納税できるの?
住宅ローン控除とふるさと納税の併用は可能です。しかし、それぞれの控除額に応じて損してしまう可能性があるため注意が必要です。
ふるさとチョイスの控除上限額シュミレーションでは、住宅ローン控除がある場合のシュミレーションもできます。住宅借入金等特別控除額を入力することで、ふるさと納税の正確な上限額が分かりますので、ぜひ試してみてください。
ちなみに住宅借入金等特別控除額とは以下の写真のピンクのマーカーのところの部分の金額になります。
育児休業中にふるさと納税してもお得になるの?
育児休業中の育児休業給付金は所得とみなされません。そのため、育児休業中にふるさと納税をする場合は慎重におこなうようにしましょう。その年給与が200万円を超える場合は、ぎりぎりふるさと納税できるラインになります。
給付金を除いた給与の総額を計算し、シュミレーションしてからふるさと納税をするようにしてください。
ふるさと納税したのに控除手続きを忘れたらどうなるの?
ふるさと納税をしたのにうっかり手続きを忘れてしまった場合、確定申告をおこなう必要があります。遡って5年以内であれば、過去のふるさと納税も確定申告できますが、その場合には寄付金証明書が必要になります。ワンストップ特例申請書の期限は翌年の1月10日(必着)までです。万が一忘れてしまった場合は、2〜3月の間に確定申告をしてください。
るさと納税を活用して地域を応援しお得を味わおう
ふるさと納税は私たち納税者の税金がお得になるだけではなく、日本全国好きな自治体を応援でき、税金について考えるきっかけにもなります。
ぜひ、皆さんもふるさと納税を活用して地域を応援しながら税金をお得にしていきましょう。
「ふるさと納税をやってみたいけど何から初めていいのか分からない…」 「ふるさと納税の仕組みを知りたい」 「ふるさと納税の始め方を分かりやすく教えて欲しい」 税金がお得になると話題になっているため、ふるさと納税をする人は年